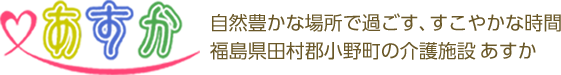デイサービスセンター あすか

私たちの想い
利用者が、その有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができ、さらに社会的孤立感の解消及び、心身機能の維持を支援します。
また、利用者家族の身体的・精神的負担の軽減を図る為の支援をします。これらを目的として、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適性なデイサービス(通所介護)を提供します。




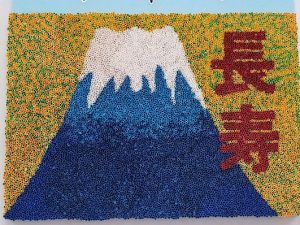


送迎車(5 台)

パワーリハビリ器

デイサービスセンター あすか 事業所運営規程
(事業の目的)
| 第1条 | 株式会社しんしんが開設するデイサービスセンターあすか(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び、関係市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の各事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、介護職員等(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護及び総合事業のサービスを提供することを目的とする。 |
|---|
(運営の方針)
| 第2条 | 指定通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 |
|---|---|
| 2 | 指総合事業の提供に当たっては、事業所の従業者は、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 |
| 3 | 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
(事業所の名称)
| 第3条 | 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1) 名 称 デイサービスセンター あすか (2) 所在地 福島県田村郡小野町大字谷津作字池ノ平52番地2 |
|---|
(職員の職種、員数及び職務内容)
| 第4条 | 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
|
|---|
(営業日及び営業時間)
| 第5条 | 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、5/3~5、8/13~15、12/30~1/3日は除く。 (2) 営業時間 午前8時30分~午後5時30分まで (3) サービス提供時間 午前9時15分~午後4時20分まで(通年) |
|---|
(事業の実施における利用定員)
| 第6条 | 指定通所介護及び総合事業の利用定員は、1日31人とする。 |
|---|
(事業の内容及び利用料等)
| 第7条 | 指定通所介護及び総合事業の実施内容は次のとおりとし、各事業によるサービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額又は総合事業にあっては、関係市町村が定める額とし、法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合分とする。 (1) 健康チェック (2) 食事の提供 (3) 生活動作の機能訓練 (4) 入浴(一般浴) (5) 送迎 |
|---|---|
| 2 | 次条の通常の事業実施地域を超えて行う送迎の交通費、指定通所介護及び総合事業に通常要する時間を超えてサービスの提供を行った場合の利用料、食事費、おむつ代、その他日常生活においても通常必要とされるものに係る費用で、利用者に負担を負わせることが適当と認められる費用については、別表に掲げる費用を徴収する。 |
| 3 | 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に関する同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けるものとする。 |
(通常の事業の実施地域)
| 第8条 | 通常の事業の実施地域は、小野町、田村市、いわき市(川前町・三和町)、平田村、川内村、郡山市(中田町・田村町)とする。 |
|---|
(サービスの利用にあたっての留意事項)
| 第9条 | 利用者は指定通所介護及び総合事業の提供を受ける際に、次の事項について留意するものとする。 |
|---|---|
| 2 | サービス利用にあたっては、日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受ける。 |
| 3 | 看護師による健康チェック後、入浴する。 (主治医による指示事項等がある場合は申し出る。) |
| 4 | 食事内容に変更が必要な場合は申し出る。 |
| 5 | 体調不良等によって指定通所介護及び総合事業の提供に適さないと判断される場合は、サービスの提供を中止することがある。 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
| 第10条 | 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。 |
|---|---|
| 2 | 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 |
| 3 | 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。 |
| 4 | 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。 |
| 5 | 事業所は、従業者に対し、個人情報や秘密保持管理のための研修を、年1回以上行う。 |
(緊急時における対応方法)
| 第11条 | 従業者は、指定通所介護及び総合事業の利用中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。 |
|---|
(非常災害における対策)
| 第12条 | 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を定期的に行うものとする。また、非常災害等が発生した場合には、速やかに利用者の避難や救出、事故の拡大防止など必要な措置を講じるとともに、予め消火設備その他の非常災害に際して必要な設備等を設け、定期的な確認や点検を行う。 |
|---|---|
| 2 | 事業所は、非常災害に対する具体的な計画(消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画)に基づき、防火管理者または非常災害についての責任者を定めるものとする。 |
| 3 | 事業所は、従業者等に対し、年1回以上避難救出等の必要な訓練を行う。 |
(衛生管理等)
| 第13条 | 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努めるものとする |
|---|---|
| 2 | 事業所は、事業所内において感染症の発生又はそのまん延の防止を図るために、必要な措置を講じものとする。 |
| 3 | 事業所は、従業者に対し、衛生管理のための研修を年1回以上行う。 |
(虐待防止に関する事項)
| 第14条 | 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 |
|---|---|
| 2 | 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 |
| 3 | 虐待の防止のための指針を整備する。 |
| 4 | 事業所は、従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回以上行う。 |
| 5 | 前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 |
| 6 | 事業所は、サービス提供中に、当該事業所又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 |
(業務継続計画の策定等)
| 第15条 | 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護及び総合事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 |
|---|---|
| 2 | 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を各年1回以上行う。 |
| 3 | 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 |
(ハラスメントに関する事項)
| 第16条 | 事業所は、適切な指定通所介護及び総合事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲をこえたものにより従業者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 |
|---|---|
| 2 | 従業者等を対象に、ハラスメントに関する知識を深めるため又、対策の周知見直し等を図るための研修を年1回以上行う。 |
(認知症ケアに関する事項)
| 第17条 | 事業所は、従業者に対し、認知症介護の資質向上のための研修を年1回以上行う。 |
|---|---|
| 2 | 新規就業者で認知症介護に関する研修を受けていない者については、速やかに認知症介護に関する研修を受ける措置を講じるものとする。 |
(その他運営に関する重要事項)
| 第18条 | 事業所は、従業者の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。 (1) 採用時研修 採用後1カ月以内 (2) 継続研修及び必要な訓練 各年1回以上 |
|---|---|
| 2 | 通所介護及び総合事業の計画書、サービス提供の記録、その他の事業の提供に関する記録を整備するとともに、完結の日から5年間保存する。 |
| 3 | 地域との協力関係を築き、住み慣れた地域で安心した介護を提供できるように、地域住民や自治組織との連携及び交流を図り、地域に開かれた運営を行うこととする。 |
| 4 | この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 |
附則
この規程は、令和6年4月1日新規制定から施行する。
デイサービスセンター あすか 事業所運営規程(別表)
〔令和6年4月1日新規制定現在〕
| 1. | 利用者の希望により、通常の営業日及び営業時間帯を超えて指定通所介護を提供する場合は、次の利用料を徴収する。 (1)1時間 500円で、提供は最長2時間までとする。 |
|---|---|
| 2. | 指定通所に介護にかかる食事費については、次の利用料を徴収する。 (1)1日あたり500円とする。 |
| 3. | 指定通所介護にかかるオムツ代については、次の利用料を徴収する。 (1)はくパンツ 150円 (2)オムツ(テープ式) 150円 (3)尿取りパット 50円 |
| 4. | 指定通所介護の提供上、日常生活においても通常必要とされるものにかかる費用については、実費徴収する。 |
| 5. | 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事情を説明した上で、支払いに同意を得るものとする。 |
感染症の予防及びまん延の防止のための指針
株式会社しんしん
デイサービスセンターあすか
1 事業所における感染対策に関する基本方針
株式会社しんしんは、経営理念に基づき、利用者に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、施設内での平常時の感染防止の対策及び感染症発生時の対策に取り組むための基本的な指針を以下の通り定めます。
(1) 経営者・管理者をはじめ、全職員が一丸となって感染症の発生及びまん延の防止に努める。(2) 国内や府内、地域の感染症状況をよく把握し、全職員が感染症に罹患しない対策を講じる。(3) 感染症が発生した場合は速やかに連絡・報告を行い施設内・事業所内のまん延を最小限に抑える対策を実施する。(4) 指針や委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させる。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下通りです。
(1)利用者及び従業員にも感染し集団感染を引き起こす感染症
インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス)、食中毒(黄色ブドウ球菌、O157等)、疥癬、結核等(2)抵抗力が低下している人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA)、緑膿菌等(3)血液や体液を介して感染する感染症
肝炎ウイスル(B型、C型)等
3 感染対策と発生時に対する取り組み
(平常時の対策)
(1)事業所内の衛生管理は感染症の予防及びまん延の防止のため施設内の衛生保持に努める。日頃から整理整頓を心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に実施し施設内の衛生管理、清潔の保持に努める。(2)ケアに関わる業務では手洗いや手指消毒、うがい、マスクの着用を徹底する。また、血液、体液、排泄物、嘔吐物等を扱う場面では防護具の使用や細心の注意を払い適切な方法で対処する。
(発生時の対応)
(1)発生状況の把握
感染者が発生した場合やそれが疑われる状況が発生した場合には感染の状況を速やかに管理者へ報告し、感染者の感染原因や行動などの必要な情報収集を行う。(2)感染拡大の防止
感染者が発生したとき、それが疑われる状況が生じたときは必要に応じて感染者を隔離し、感染者に直接対応する職員を限定し、看護師の指示を仰ぎ施設内の消毒を行う。
感染対策の手引きやマニュアルに従い感染防止策をとること。(3)関連機関との連携
感染者の発生時には必要に応じて地域の医療機関や市町村の関係機関へ報告。
報告が義務付けられている感染症については速やかに行政や保健所へ報告し指示を仰ぐこと。
4 感染防止対策委員会の設置
感染症の予防と早期発見に加え、感染症が発生した場合はそのまん延を防止するため感染防止対策委員会を設置する。感染防止対策委員会は各事業所より幅広い職種によって構成する。
- 管理者
- 生活相談員
- 看護職員
- 介護職員
- 厨房職員
- その他管理者が必要と認める者(外部の専門家)
- 委員会は半年に1回開催し感染症発生時には必要に応じて随時開催する。
- 施設内の具体的な感染対策の立案
- 指針、マニュアル、組織の整備
- 職員への感染対策の研修、訓練の検討
- 利用者、職員の健康状態の把握
- 事業所内の感染症対策実施状況の把握及び評価
- その他、感染症対策に関すること
5 職員への研修
事業所は、従業員に対し感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発をするとともに衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的として「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シュミレーション)」を次のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)(2)新規採用者へ感染対策の基礎に関する研修を実施する(必須)(3)訓練(シュミレーション)を年1回以上実施(4)研修の内容、日程、参加者を記録し保存する
6 指針の閲覧
本指針を事業所内に掲示すると共に、利用者及び家族等から希望があった場合にいつでも閲覧できるよう事業所のホームページに公表する。
7 その他感染症対策の推進について
本指針は委員会において定期的に見直し、必要に応じて改訂する。
附則
この指針は、令和6年4月1日から施行する。
ウォーターベッド型マッサージ
水による「癒し」「刺激」「治療」
期待できる効果
- 末端の血行促進
- 筋肉の疲労物質の除去。
- 心と身体のリラクゼーション
- 血液循環の向上
- リハビリテーションへの応用
- ストレス解消

一日のプログラム

ご利用案内
通所介護予防(総合事業)
要支援1・2の認定をうけた方
お一人お一人にあった生活機能拡大のためのプログラムを作成し、運動機能向上並びに口腔機能向上を行います。
通所介護
要介護1~5の認定をうけた方
お問い合わせ・ご連絡先
詳しいお問い合わせはこちらまで
TEL:0247-71-1182
FAX:0247-71-1183
福島県田村郡小野町大字谷津作字池ノ平52-2